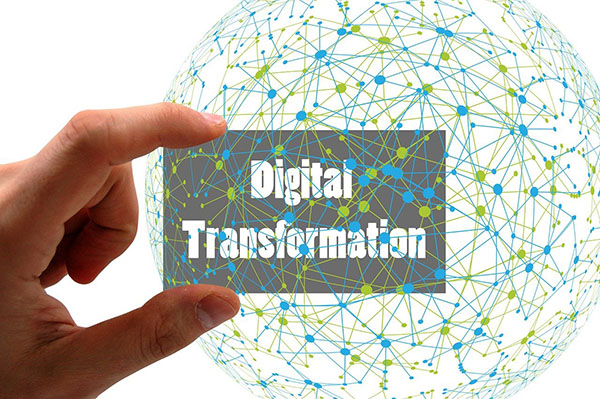DXとは、
デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略で、デジタル技術やデータを活用して、業務プロセスやビジネスモデルに革新的な変化をもたらし、市場における競争優位性を確立することです。
■マイナンバーカードに感じた違和感
2013年、第2次安倍内閣のもとで「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」、いわゆるマイナンバー法が成立しました。
翌2015年10月以降、個人番号の通知が始まり、2016年1月から社会保障や税の分野で運用がスタート。
同時に「マイナンバーカード」の交付が始まりました(取得は任意)
正直、当時の僕はこの制度をすんなり受け入れることができませんでした。
「奴隷カード」と揶揄する声もあり、何よりも政治に対する不信感が拭えなかったのです。
なにせ、先進国の中で「30年間サラリーマンの平均給与が上がらなかった国」は日本だけ。
その現実を知るほど、国のデジタル化に疑問を抱いていました。
■マイナ保険証、そして「観念」
そして今度は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化――「マイナ保険証」です。
2023年6月に法案が成立し、2024年12月2日から新しい保険証の発行は停止され、原則としてマイナ保険証が基本になります。
つまり、もう「待ったなし」
この12月からは、マイナ保険証がないとスムーズに医療を受けられない時代に入ります。
そこで僕は、発想を転換しました。
「どうせ避けられないなら、学ぼうじゃないか」と。
そして辿り着いたのが、世界一DX化が進んだ国「エストニア」でした。


エストニアという国 ― 世界最先端のDX社会
1991年、旧ソ連から独立した小国エストニア。
現在、行政業務の99%が電子化されています。
市民は24時間365日、自宅のPCやスマホからあらゆる行政手続きが可能。
引っ越し、納税、会社設立、選挙投票までオンラインで完結します。
たとえば。。。。
-
子どもが生まれた瞬間、病院が自動的に出生届をオンライン提出。10分後に「おめでとう」メールが届く。
-
銀行振込は99%オンライン。
-
税務署が銀行口座の動きを自動で把握し、「確認→承認→完了」まで3クリックで確定申告が完結。
-
免許証・車・銀行口座・健康情報がマイナンバーで統合管理。
-
「免許不携帯」の概念すら存在しない。
つまり、国民ID(マイナンバー)が社会のハブ(中心軸)になっているのです。
エストニアの国民は、スマホとマイナンバーカードだけで生活が成り立つ。
それでいて、セキュリティも極めて堅牢。
二段階認証と分散型サーバー構造によって、これまで一度も大規模ハッキング被害が発生していないという事実。


エストニアのすごいところ3選
① ネット弱者を切り捨てない。
オンライン投票が主流でも、アナログ投票所を必ず併設。
「便利」と「公平」を両立させている。
② プロアクティブ(先回り)型行政。
国民が申請しなくても、行政が自動で処理する。
子育て給付金も申請不要で自動振込。
「困っている」と入力すれば、行政が検索し、解決策を提示する。
③ 個人情報は「国家のもの」ではなく「個人のもの」
医療データ、レントゲン写真、検査記録まですべて個人の管理画面に集約。
政府は「サーバーを貸しているだけ」
官が民を監視するのではなく、民が官を信頼できる仕組みができている。
■おわりに ― 日本の未来へ
エストニアのDX化は「効率化のための技術」ではなく、「信頼」を土台とした社会設計です。
デジタル化の目的は「人を楽にすること」
「ITで儲ける」のではなく、「無駄をなくし、時間を取り戻す」こと。
マイナンバーカードをめぐる議論の中で、僕たちはつい「管理される側」としての視点になりがちです。
しかし、エストニアのように「市民が自分のデータをコントロールできる社会」へと進化できたなら、
それは「監視社会」ではなく「自由社会」への進化なのかもしれませんね。
📺参考動画:
YouTube|エストニアのDXが凄すぎる件